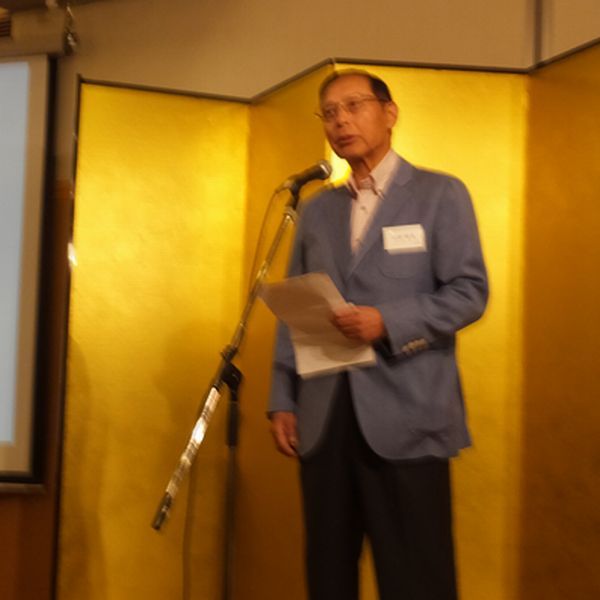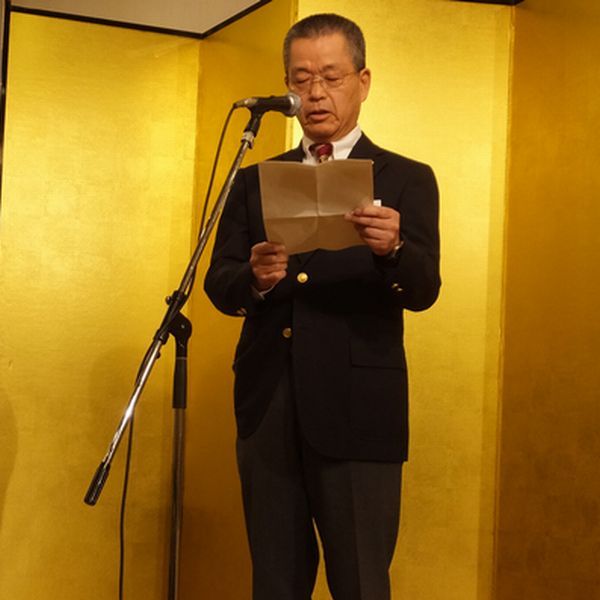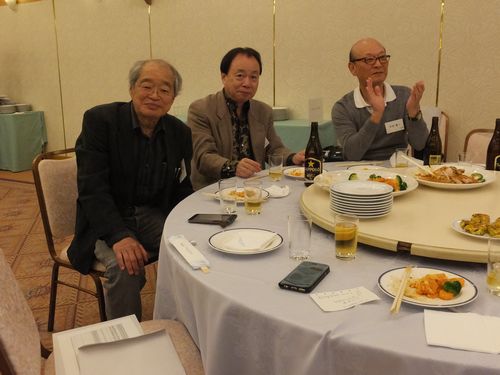平成28年度第61回東京双松会総会・懇親会報告
平成28年11月10日
去る10月15日アルカデイア市ヶ谷(私学会館)において、平成28年度の東京双松会の総会が開催されました。最近の異常気象により、当日の天気が気がかりでしたが、幸いにして、秋晴れに恵まれました。参加者は例年に比べて若干少なめでありましたが、山陰テレビによる取材などもあって、例年とは違った意味で、活気に満ちた総会になりました。
以下に総会の模様を報告いたします。
|
|
今年の東京双松会にはテレビ取材が入りました
松江市の山陰ケーブルテレビジョン(通称:マーブルTV)のニュース番組の中で総会の模様が取り上げられました。
同時に正月に放映される「開局30周年特別記念番組のための取材が行われ、10名位の会員がビィデオ・インタビューに応じられました。
番組名は「ありがとうでつなぐ NEW YEAR 夢駅伝」
松江の皆さん! 是非ご覧ください!
|

受付風景 |

司会 本田久子さん((昭和60年卒) |
中村康一事務局長((昭和40年卒)の開会の宣言を受けて、芦田昭充東京双松会々長(昭和37年卒)が登壇され、
スポーツ・マンらしい挨拶をされました。
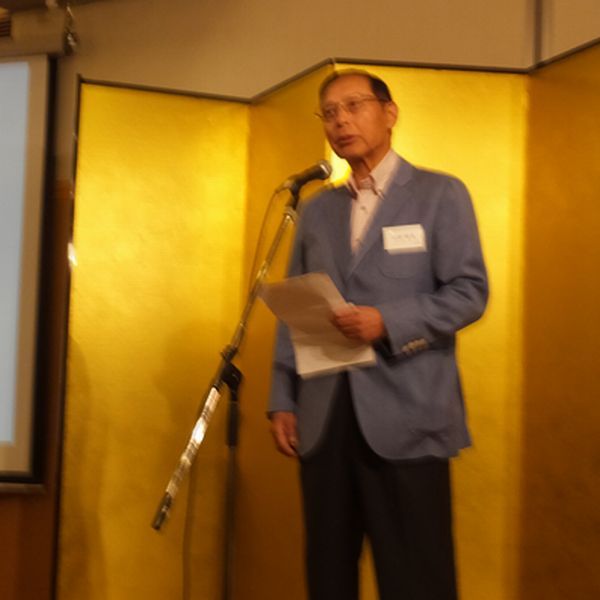 芦田昭充東京双松会々長(昭和37年卒)の挨拶
芦田昭充東京双松会々長(昭和37年卒)の挨拶
本日は、第61回東京双松会総会に際しまして、たくさんの会員の皆さん、また遠路、双松会役員の方々にご出席賜り、ありがとうございます。
さて、本日の講演でございますが、東京中央日本語学院の講師をなさっています森田六朗様をお招きしました。森田様は、北高38年卒業、14期でございます。本日の演題は、「近くて遠い国 中国で12年暮らして」ということでございます。中国は地理的、それから歴史的には非常に近い国ですけれども、遠い国です。本当にその遠さを感じます。
近ごろ、インバウンドと称して中国から訪日客がふえておりまして、昨年が500万人、ことしは500万人を超えるだろうといわれておりまして、幸いなことに、日本を訪問した方々は、日本に対して非常にいいイメージをもって帰っておられます。ですから、毎年500万人がずっと積み重なれば、そういう方々が中国に帰って、やはり日本は本当にいい国だ、残虐性とかは決してない国だと言ってもらえば、草の根の部分で日本に対する見方が変わっていくのではないかということを私は期待しております。
さて、ちょっとスポーツ関係のお話をさせていただきたいと思います。実はことしの6月、名古屋で日本陸上競技選手権大会が開かれました。私は日本陸連の評議員をやっておりますので、観戦したのですけれども、皆さんご承知ですかね、女子800メートルで松江北高の福田翔子選手が優勝しました。800メートルですから、大体固まって走っていたのですけれども、残り250メートルでスパートをかけたのです。後半へたりますから、私はちょっと早いかと思ったのですけれども、全然スピードが落ちないのです。コーナーを回ってホームストレッチに入ったときには、さらにスピードが増して、2位に5メートルぐらい差をつけて圧勝です。これは実業団も大学生もいます。そういうのを相手にして高校生が優勝したわけですから、これはすごいと思います。何としてでも福田翔子選手には東京オリンピックに出て活躍してほしいと思っております。
同じ大会で、女子400メートル。これは松江商業出身の青木選手が優勝しました。ですから、女子の400、800の2つを島根県出身の選手が抑えました。これはすばらしいことで大変興奮しました。
リオのオリンピックでは、ご承知のようにテニスで錦織選手が銅メダル。女子レスリング75キロ級の渡利璃穏選手は松江出身です。残念ながら2回戦でブラジルの選手に負けたのですけれども、頑張ったのです。また、出雲市出身の女子ホッケー・錦織えみ選手。DFで最年少でゴールを決めました。
それから、パラリンピックですけれども、男子車椅子テニスの三木拓也選手。出雲市出身ですけれども、男子ダブルスの3位決定戦に進みました。残念ながら銅メダルはとれなかったのです。
それから、男子400メートルリレーで2位になりましたけれども、そのときの1人が日本の短距離のホープ桐生祥秀選手。桐生選手は島根県ではありませんけれども、大学に入ってから彼を育てたのが土江さんという出雲高校出身の東洋大の教授なのです。土江さんもかってのオリンピック選手で桐生選手をずっとサポートしている。何とか100メートルで9秒台を出して欲しいものです。
それから、この間、出雲大学駅伝が行われましたけれども、このとき2位になったのが山梨学院なのです。この中に2人島根県出身の選手がいたのです。
話がちょっと飛びますけれども、相撲では隠岐の海が金星を2つとりまして、殊勲賞をとった。このように国際的、あるいは純国内的なレベルで島根県絡みの選手が活躍しています。
今回はスポーツだけしゃべりましたけれども、実は、他の分野でも島根県出身の方がいろいろな分野で活躍されています。話が長くなりますから、これはちょっと割愛させていただきますけれども、島根県は人口70万人をちょっと切りましたが、このように優秀な人材を輩出しているということは刮目すべきことではないかと思います。
幸いにして、島根県の出生率は1.8。アベノミクスで2030年1.8を狙っていますが、島根県はもう達成しているのです。ですから、島根県の目標は2ぐらいにしなければだめです。沖縄が2に近いのです。ですから、沖縄を抜くというぐらいで、優秀な人材が出てきますから、それを県内にとどまってもいいのですけれども、とどまらず、いろいろなところに出て活躍していただく。そういう人材を育てるベースになっているのが松江北高校であると私は思います。
今後ますます松江北高校が頑張って、人材を輩出する。そして、ここにいらっしゃるように県外に出て活躍していただく方々がもっとふえる。皆さん、ぜひ健康でやっていただきたい。本日ご参加されているご年配の方々、健康維持には歩くことが一番大切なようですので、とにかく毎日歩いていただくことを心がけて、ぜひ健康を維持していただきたいと思います。
以上で私の挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。
|
次いでご来賓の泉雄二郎校長先生(昭和50年卒)が登壇され創立140周年を迎えての諸企画や現在の北校生の活躍振りを
紹介されました
 泉雄二郎校長先生(昭和50年卒)のご挨拶
泉雄二郎校長先生(昭和50年卒)のご挨拶
北高の校長・泉雄二郎でございます。本会には3回目の出席となりました。まず、皆様のご健勝なお姿に接し、この1年、健康な日々をお過ごしになられたことを大変うれしく思います。おめでとうございます。
今年は創立140周年を迎えております。これに向けてさまざまな取り組みをしております。同窓会名簿(平成28年版)と、ここ10年の歴史を刻んだ10年史の冊子を刊行いたしました。11月12日には記念式典を挙行いたしますのでぜひご参加いただきたいと思います。
総会では、高24期、株式会社カゴメの寺田直行社長様に「カゴメの長期ビジョンとシニアの食育」をお題にご講演いただきます。シニアの食育でございますので、ぜひ会場に足を運んでいただきたいと思います。
続いて、懇親会でございますが、実は北高に非常に古い時代の8ミリ映像が残っておりまして、これをデジタルの形にリメイクいたしました。その中の1本を当日上映する予定でおります。内容は、昭和40年ごろだと思いますが、宍道湖1周のレースのビデオでございまして、カラーです。個人が特定できるほどの鮮明度で映っておりますので、あれ俺だというような映像があろうかと思います。
さらには、音楽部が演奏いたしますけれども、3年生の中に作曲家を目指している生徒がおりまして、校歌を140周年記念バージョンに編曲いたしまして、これを吹奏楽、合唱、箏曲、弦楽が合同で演奏したビデオがございます。これを上映いたす予定でおります。
それから、翌13日でございますけれども、鳥取西高校を招いて、旧制の鳥取中学校でございますが、松江球場にて親善試合を行うことにしております。ダブルヘッダーを組んでおりまして、現役とOBが戦うことになっております。この日の午後、音楽活動をしておられるOB、いわゆるおやじバンドと現役のバンドがコラボレーションしまして、北高音楽の集いという催しも計画しているところでございます。上下の世代をつなぐ試みとして企画されたものでございます。
8月下旬に学園祭が行われましたが、ことしの生徒たちが抱えたテーマは「礎〜先駆者よ、回せ歴史の歯車を 鳴らせ未来への汽笛を」でありました。旧制中学70年、新制高校70年の歴史の上に新しい北高の姿を生徒たちは模索し始めております。2030年の世の中を想定し、そこで生きる若者の育成には何が必要かを熟考し、不易と流行を踏まえた上で新しい高校教育の在り方を構想しております。
本校における不易と流行は、質実剛健の精神をどう解釈し、カリキュラムマネジメントを行うかにかかっております。私は、「質」イコール自身の内面を高める学び、「実」培ってきたことを生かす行動、「剛健」困難を乗り越えるタフネスと解釈しております。
少し先の話になりますが、平成32年度から新しい学習指導要領がスタートするのでありますが、主体的で対話のある深い学び、さらに社会に開かれた教育課程が基本として掲げられております。これを質実剛健的に解釈いたしますと、みずからとりにいく学びを継続すること、社会に目を向けどう貢献すべきかを考え行動すること、上り切る経験を重ねてタフネスさを養うこと、この3つがこれからの北高の目指すところではないかと思っております。
2年前、私はここで、最近北高生は元気がないということを申しましたが、2年後、北高生は少し元気になったかなという感じがいたします。県総体、総合、2連覇いたしました。バドミントン、登山、弓道、ボート、新体操、陸上が全国大会に出場いたしました。先ほど芦田会長様のお話にもございましたように、陸上競技では女子800メートルの3年生、福田翔子が日本選手権、さらにはインターハイを制し日本一となりました。東京オリンピックを射程に入れた選手でございます。
文化系は、放送部、美術部、囲碁、将棋、百人一首かるた、弁論、弦楽が全国大会に出場いたしました。百人一首かるたの読首、札を読む部門ですが、全国一になりました。その他にも歴史愛好会というグループがございまして、この発表が全国3位。それから、スーパーコンピュータプログラミングコンテストという大会がございまして、ことし全国大会に初出場いたしました。科学の甲子園、全国19位、これは島根県勢としては最高の成績でございました。というように、生徒個々の能力を生かしながらさまざまな分野で活躍しているところでございます。
多くの皆様が過ごされました川津校舎時代、11クラス各55人といった非常に大きな規模の時代があったと聞いております。全校生徒が1,500人を超えるような松江北高。現在、在校生は906名でございます。ことし1つクラスが減りまして、南北東のクラス数は北高7、南高7、東高6でございまして、これが維持できるかどうかも怪しい大変寂しい状況にございます。入学については東高ができましてからは各小学校の校区によって線引きが行われています。29年度の入学者選抜から、自由枠といっていますけれども、どこでもいいという枠が定員の20%まで緩和されます。このことは恐らく南北東に少なからず影響を与えると思っておりまして、その際、一番入学したい高校と中学生が憧れる目標とする松江北高であることがこれまで以上に求められております。
私は、北高はリーディングスクールであれといっております。全県をリードする勢いのある学校であるという意味であります。そこを目指しまして、一層存在感を高めていくことが必要な時代を迎えているということでございます。
本年度は、春休みに6名がアメリカ東海岸の研修に出かけました。夏休みには6名がアメリカの短期留学をしております。秋から2名が1年間カナダに留学しておりまして、1人アメリカから帰ってまいりました。学校の狭い範囲にとどまらず、足もとの地域、日本、さらには世界へと生徒たちの関心が広がっているところでございます。
140周年を期して造成していただきました世界の人たれ北高基金には、皆様方から早400万円近い浄財をお寄せいただいております。目標は1,000万円でございますが、留学や留学生との交流事業、課題研究、あるいは双松会のグローバル人材による講演会開催などに基金を活用し、新しい北高を構築してまいりたいと思います。
次の70年、北高を社会、あるいは世界に開き、風を吹き込みたいと願っております。諸先輩におかれましては、人生の経験、国内外でのご活躍の姿を現役生に示してやっていただきたいと思います。ぜひお知恵と皆様がおもちのネットワークに生徒、あるいは教職員をつないでいただきますようお願い申し上げます。
以上、近況報告とお願いをもちまして、ご挨拶とさせていただきます。本日の盛会、まことにおめでとうございます。
|
されました。
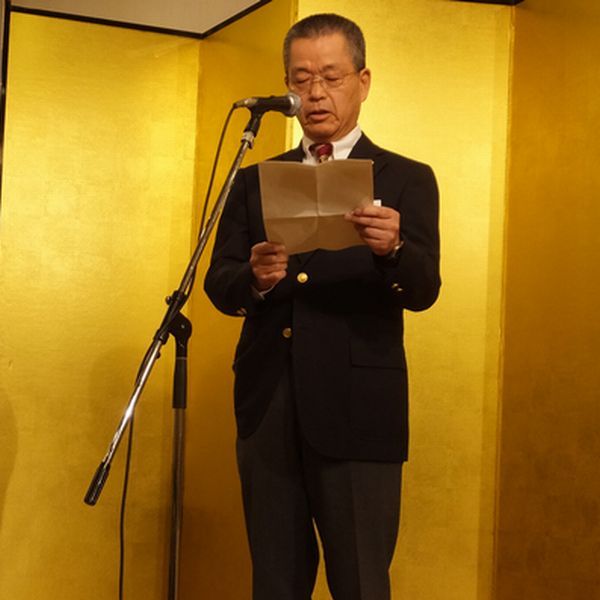 勝部昌幸双松会副会長(昭和45年卒)のご挨拶
勝部昌幸双松会副会長(昭和45年卒)のご挨拶
双松会副会長の勝部昌幸と申します。北高21期の卒業です。北高校長時代、二度ほど東京双松会にお邪魔しました。本日、金津会長は所要のため欠席です。会長からは、くれぐれもよろしくとのことでございます。
双松会には東京双松会からもたくさんのご理解、ご援助をいただいており、本当にありがとうございます。昨年は「北高の緑を守る基金」、それから今年度からは「世界の人たれ北高基金」ということで、心のこもったご寄附をいただいております。
今日は花森安治という人の紹介をして挨拶に代えたいと思います。ちょうど、東京オリンピックの1964年、雑誌「暮しの手帖」75号に松江を特集した記事が載っております。
9月までNHKの朝ドラ「とと姉ちゃん」で高畑充希さんが演じていたのが小橋常子(モデルは大橋鎭子)。彼女と一緒に雑誌「あなたの暮し」(「暮しの手帖」がモデル)を立ち上げたのが唐沢寿明さん演じる花山伊佐治、そのモデルになったのが花森安治です。
花森安治は1911年(明治44年)、神戸生まれです。神戸の旧制中学を卒業後、旧制松江高校(現島根大学)に入学し、学生時代を松江で過ごしています。その後、東京帝国大学に進学して東京に勤めます。そして、第二次世界大戦が始まります。奥様は天神町の呉服問屋の娘さんで、彼はとても松江が気に入っていたということです。
その「暮しの手帖」に、彼はこのような文章を寄せています。
「まちの真ん中に城がある。その城の周りを森が囲み、その森をぐるっと抱いて堀がめぐっている。堀はゆったりと水をたたえ、蔦葛にびっしりと覆われた城の石垣と四季とりどりの森の色を逆さまに写している。堀端には昔ながらの武家屋敷がしいんと影を落としている。まちの中を幾つも掘り割りが流れ、掘り割りに沿った家並みは、白壁の土蔵を挟んでひっそりと続いている。道は突き当たっては曲がり、すぐまた真っ直ぐ伸びて、その掘り割りにかけられた橋を幾つも渡る。ふと横丁の路地をのぞくと、狭く薄暗い突き当たりがからりと開けて光っている。湖である。行ってみれば、手の平にでも乗せられてしまえそうな小ぢんまりとまとまったまちである。まちの目ぼしいところは、縦に歩いても横に歩いても、ものの小一時間もあれば行き着いてしまう。もし日本の城下町というものの精巧な模型をつくろうと思えば、多分こんな風なまちができ上がるかもしれない。」
花森安治は松江の出身ではないですが、松江の空気や、静かな時の流れを表現してくれていると思います。今でも、この雰囲気は松江のまちに残っております。
皆さまは1年に一回ぐらいは帰られていると思いますが、こういう話を何でするかといいますと、ことしは母校創立140周年です。ぜひとも懐かしい松江のまちに帰っていただいて、そして旧交を温めていただければと思っております。
本日はご盛会、本当におめでとうございました。
(一部加筆、東京双松会事務局)
|
ご来賓の挨拶が終わったところで中村事務局長の27年度の活動報告、矢田修治会計担当(昭和46年卒)の会計報告、
宮城由美子監事(昭和53年卒)の監査報告があり、満場一致で承認されました。
会は順調に進み、恒例の講演に移りました。
講師は芦田会長より紹介のありました東京中央日本語学院講師、森田六朗氏(もりた ろくろう/昭和38年卒・北高第14期)で演題は
「近くて遠い国-中国で12年暮らして」
森田氏は北京の大学で日本語教師を勤めるかたわら中国の若者に剣道を指導されました。その貴重な体験や実生活を通して得られた視点から「中国の風土と習慣」「日中の文化的差異」など興味深いテーマを本音で語って頂きました。
(参考・森田氏著書)
『北京で二刀流』(現代書館)、『日本人の心がわかる日本語』(アスク出版)
|
森田六郎氏の講演が終わったところで、懇親会に移りました。石倉義朗当会顧問が乾杯の音頭をとられるや、いつものこと
ながら、たちまちにして座が和み、テレビ撮影が行われていることも忘れ、あちこちに懇談の輪が広がりました。
以下に盛会の模様を写真で紹介いたします。
ココをクリックすると年代別の写真をご覧になれます。
報告(HP管理人:福間三郎)
|